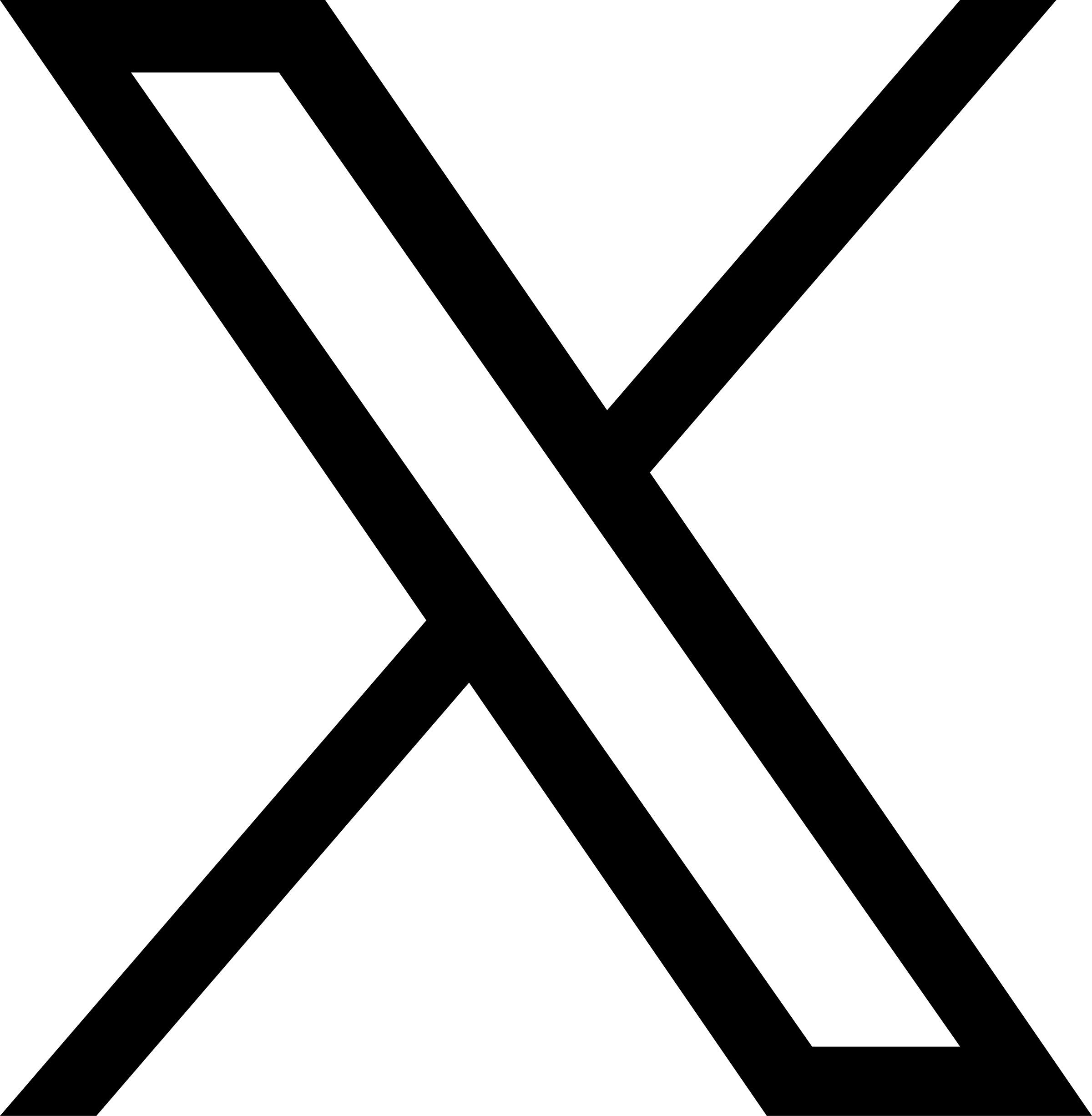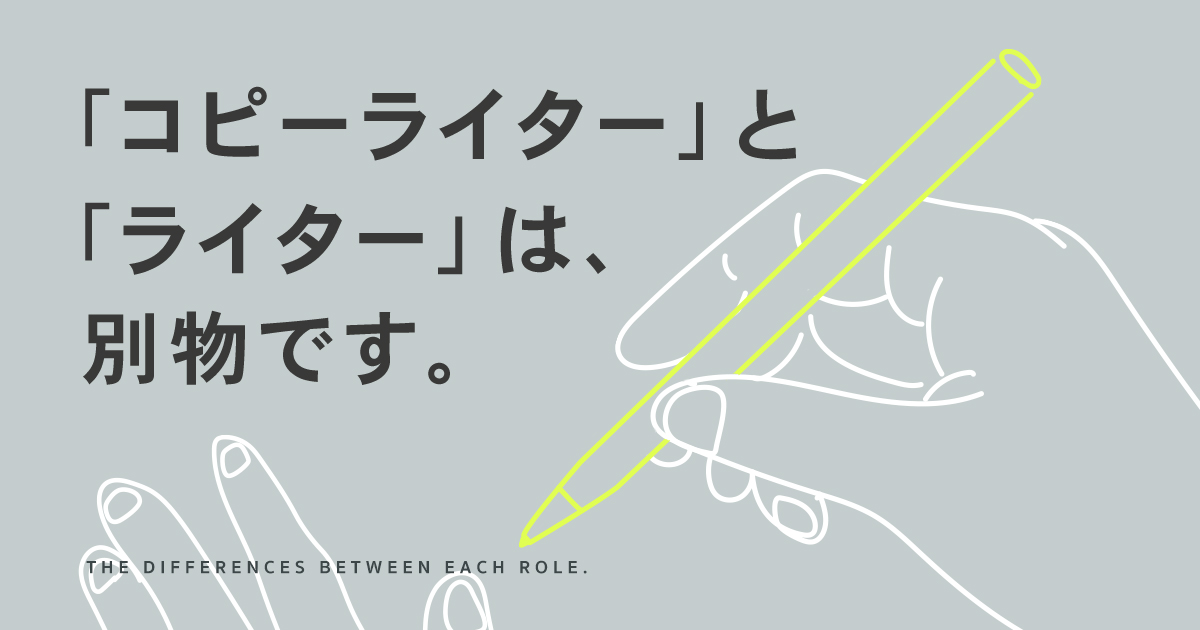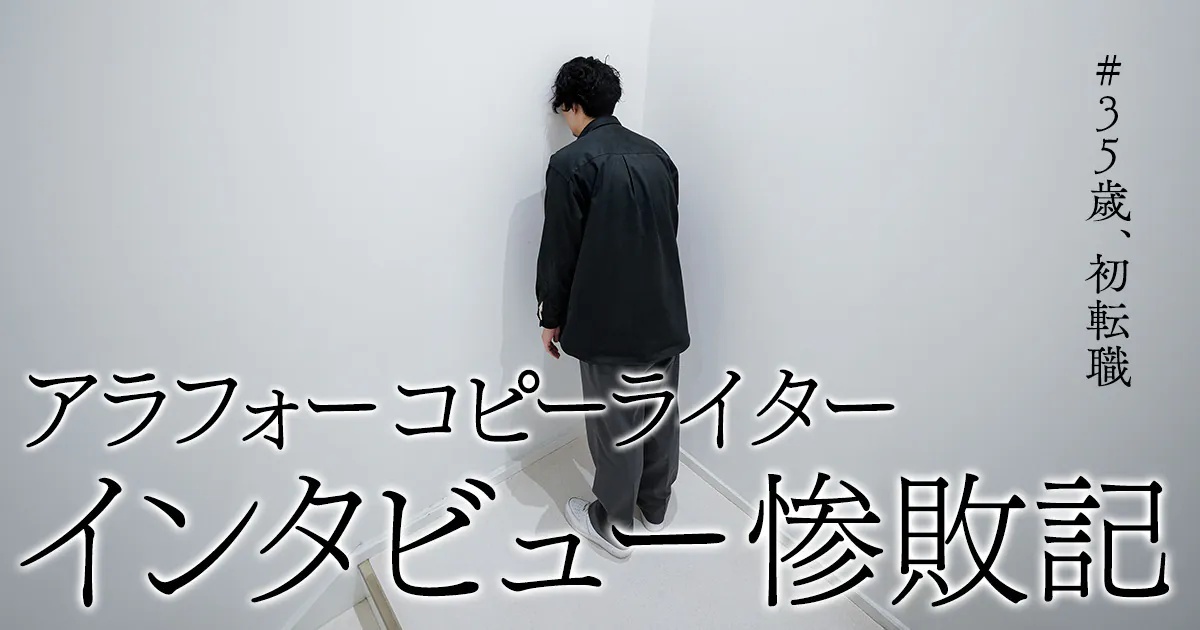
「うーん…大丈夫ですか?書けそうですか?」
クライアント先の社長からパソコンの画面越しにそう聞かれたとき、背中の真ん中からじわぁっと汗が吹き出て、尾てい骨まで流れてくるのがわかった。
リモート取材を開始して60分ほど経ったころだろうか。社長のおっしゃるとおり、満足のいくライティングができる情報を聞けている自信はなかった。原因はもちろん、ぼくの取材力が足りなかったためだ。
いたらない取材にも関わらず、「この話は社員に聞いてもらうのがいいかもしれないですね」と、社長はやさしくフォローをしてくださった。
その後のことは、あまり覚えていない。お通夜のように終わらせてはいけないという、なんの足しにもならない責任感から、妙にテンションの高い「ありがとうございました」というお礼を述べて、取材は終わったと記憶している。
ごあいさつが遅れました。トゥモローゲートでコピーライターをしている小澤と申します。
経歴をカンタンにお伝えしますと、前職では健康食品などを販売する通信販売の会社で営業企画として10年働いておりました。そして、昨年9月からトゥモローゲートのコピーライターとして入社。実は35歳にして初転職となりました。ブランディングツールの制作で、取材とライティングを担当しています。
冒頭に書いたのは、ある日の取材の様子。後日アンケートや追加取材をおこない、なんとか乗り切ることはできたものの、自分の取材力の低さにひどく落ち込みました。
コピーライターといえば、書く仕事という印象が強いかもしれません。ですが、それ以上に聞く仕事でもあります。理由はシンプルで、わかっていないと書けないからです。
本記事では、ぼくのインタビュー惨敗記をとおして、いかに取材(=聞く技術)が重要かをお伝えできればと思います!
【CASE01】事業理解が浅く、会話が噛み合わない…
とある不動産会社のコーポレートサイト制作にあたり、事業内容の取材をした時のこと。事業は大きく「賃貸」「売買」「管理」の3つに分かれていた。「賃貸」は言わずもがな、お部屋探しの支援。ぼく自身、一人暮らしの経験があったので、サービスのイメージはすぐに湧いた。理解に時間がかかったのが「売買」と「管理」だった。
この2つは「賃貸」とは違い、不動産を所有するオーナーが顧客に含まれる。
一般的に「管理」の業務は入居者のクレーム対応などを請け負っていることが多いのだが、この企業はそこに留まらず、オーナーが所有するマンションや一軒家のリノベーションを提案することで、空室を解消したり賃料や売値を上げて、資産価値を高められる強みを持っていた。
恥ずかしながら当時、このビジネスの仕組みを理解できていなかった。顧客は誰なのか。どんなことに困っているのか。なぜリノベーションを提案するのか。それがなぜ資産価値の向上につながるのか。それらを理解しないまま、事前に用意していた質問だけをイタズラに消費し、以下のような取材になっていない取材を続けていた。
「リノベーションの何がメリットなんですか?」
「んーっと…僕らにとってですか?お客様にとってですか?」
「あ、失礼しました…。お客様にとってです」
「不動産の価値が高まって収益が上がるからですね」
「あ、なるほど。御社の売上が上がるわけですね」
「ん?いやいや、オーナーさんですよ。まぁ結果的にうちも上がりますけど…」
「なるほど…失礼しました…。えーっと、次はですね…」
(……大丈夫かな)
わかりやすくするために、あえて酷めに再現している部分もあるが、取材相手が感じた不安を表現したものとしては、オーバーではないと思う。
「めっちゃアホやん」と思われるかもしれないが、慣れない環境で緊張が加わると、一気に思考レベルが落ちる経験をしたことはないだろうか。例えるなら、クイズ番組で小学生でも答えられる簡単な算数の問題が解けないタレントと同じ状況だ。
だが、これはクイズではない。取材だ。むしろ聞く場所である。では、なぜ聞かなかったのか?
一言でいえば、プライドだった。「知らないこと」が、恥ずかしかったのだ。
結局、取材は同席していた5つ年下の上司に巻き取られた。さらに落ち込む。その後、フィードバックで受けた言葉は恥ずかしさを超えて、情けなさに変わった。
「わからないことをわからないまま進めるのが、一番相手に失礼ですよ」
全くもってその通りだ。取材中に相手を不安にさせることはもちろん、わかっていないことは書けないのだから。わからないことは、勇気を持ってわからないと言うべきなのだ。
もちろん最低限の業界知識は学んでおく必要はある。だが、たった数日間でその道のプロが持っている知識量を超えることは、不可能に近いだろう。つまり、わからないことは決して恥ではないのだ。
いいものを書くために、100%理解したと自信を持てるまで、遠慮なく聞く。取材の基本姿勢を学んだ経験だった。
【CASE02】想定外の状況に対応できず、静かにパニくる
「取材はLIVE」だと、つくづく思う。始まったらもう止められない。だから徹底的に準備するし、当日のシミュレーションを頭の中で何度も繰り返す。しかし、想定通りに進んだ取材は今までに一度もない。
ある企業の取材で、1名だと聞いていた取材相手がいきなり3名現れた。その瞬間、誰に話しかけるべきかわからなくなり、開始2秒でパニックに陥ったことがある。
ボクシングの試合に例えると、ゴングが鳴った瞬間にストレートをお見舞いされて、膝をついてダウンしている状態だ。立ち上がろうとするが、すでに戦意(=取材に臨む気合い)は失われかけている。セコンドにいるコーチ(=取材に同席している5つ年下の上司)をチラッと見ると、無慈悲な表情でぼくを見つめていた…。
どうやら助けは期待できないようだ(そりゃそうだ。まだ2秒しか経っていない)。弱みを見せるわけにはいかない。さも想定通りであったかのように笑顔をつくるが、内心は子鹿のように震えている。こうした内面の動揺を必死に表に出すまいとしている状態を、ぼくは「静かにパニくる」と呼んでいる。
静かにパニくったぼくは、想定していた1人だけに質問を乱暴に投げ続け、他の2名を置きざりに取材を進めてしまった。無礼なやつだ。そしてそれは、取材はさらに混乱させた。「あ、それは私が回答しますよ」「え?今の質問は私にですか?」といった具合に。気がつくと、タオルが投げ込まれていた。5つ年下の上司に取材を任せる羽目になった。
この取材の何がダメだったのか。
冷静に考えれば、複数名の参加はありえる話だ。取材対象者が部下を勉強のために同席させることはめずらしくない。だが、当時のぼくはその想像が働かなかった。理由は、「取材はLIVEである」という前提が欠けていたためだ。
静かな環境で、座りながら落ち着いて取材ができるとは限らない。なんらかの理由で取材時間が短くなることもある。実際、小さなお子さんを抱いている状態の方を取材したり、撮影現場へ移動するわずかな時間で歩きながら取材することもある。現場では何が起こるかわからないのだ。その場にあわせて取材の方法を柔軟に変える必要がある。
今回のケースでいえば、まず3名のプロフィールや立場を整理し、誰にどの質問をするのが最適かを見極めるべきだったのだろう。また、取材のゴールを参加者全員と共有し、改めてスタートすべきだった。複数名での取材(=よくある形式としては対談)では、バラエティ番組で活躍する名司会者のような、場を回すスキルも求められるのだ…。
【CASE03】重要な数字を聞き漏らし、再取材…
原稿を書いているときに、ふと思った。
採用サイトの制作で、社員さんの活躍ぶりを紹介するページを書いていたのだが、どうも話がぼんやりしていて、おもしろみがない。
「過去最高の結果でした。」
「猛スピードで取り組みました。」
「大きなプロジェクトで…」
5つ年下の上司に原稿を見せてみると、その原因がはっきりとした。
「これは、どれくらいの期間で目標を達成した話なんですか?」
「何人で取り組んだプロジェクトだったんですか?」
そう、この原稿には「数字」が欠けていたのだ。そのため、一見すごい話をしているようで、何も伝わらない文章だったのだ。
「音源を…確認してみます!」と、祈るような思いでデスクに戻る。音源を聞いてみるも、肝心な情報はまったくない。というか聞けていない。「ああー!!へったくそなインタビューしやがって!!!」と心の中で、自分を罵倒する。落ち込む。迫る〆切に、どんどん焦る。
血迷ったぼくは、検索エンジンで社員さんの名前を検索し、それらしき数字がないか探した(稀ですが、過去の取材記事や求人サイトに材料となる数字や実績が見つかることもあり、それを拠り所にして書き切ることができたケースも1つや2つあります)。
しかし、血眼になって探しても、ないものはない。
もう聞くしかないのだ。
社内のプロジェクトリーダーに頭を下げて再取材の依頼をし、先方にアポイントを調整してもらう。快く調整してくださるクライアントには感謝しかない。無事、再取材で解決することができたものの、あきらかに生産性の悪い動きだ。
また、再取材は意外とデメリットも多いと感じる。より詳しく話が聞けるメリットがある一方で、取材相手の感情の起伏が初回よりも見えにくいからだ。おそらく取材というより確認の意味合いが強くなるため、事務的な会話にならざるを得ないからだと思う。CASE02で述べたとおり、やはり取材はLIVEなのだ。
ちなみに、数字のヒアリングはその話題を取り上げるべきかどうかの判断基準になったりもする。というのも、社員紹介の取材では大抵の場合、自分の実績を謙遜されることが多い。
「いやいや、大したことないですよ」
「でも、このくらいのことは他の社員もやってますよ」
「胸を張れるような実績って、ないんですよね〜」
これらの回答は嘘ではないが、あくまでご本人の評価であり、客観的な事実からズレていることもある。謙遜が真実を見えにくくするケースはよくあるのだ。
そんな時、数字を聞けば実態がはっきりする。そして、その数字が社内や業界全体においてどのくらいの位置にあるのかを聞けば、実績や仕事のスケール感を正しく伝えることができるのだ。
「いい質問ですね」と、言ってもらえる取材を目指して
この記事を書くにあたり、トゥモローゲートに入社してからの取材本数を数えてみました。結果、1年間で約90本ありました。しかし、そのなかで「100%うまくいった」と自信をもっていえる取材は、ひとつもありません。
では、どうなれば「いい取材ができた」といえるのでしょうか。そんな疑問を、10年以上コピーライターをされている方と食事に行かせていただいたときに、聞いてみたことがあります。
そのときにおっしゃったことが、取材の心構えの一つになっているので、ご紹介します。
では、「いい質問」とはどんな質問なのか。
お話を深掘りするなかでたどり着いたのが、取材相手に少し考えてもらうような(=いい意味で困らせる)質問ではないか、ということでした。なぜなら、そこから生まれる回答はきっとまだ、世の中に出ていない話だからです。そんな取材ができてこそ、取材者として価値ある時間を生み出せたといえるのかもしれません。
ちなみにその方は、こうも付け加えておられました。
「それでも100点とは思わない。いつも終わった後に、もっとできたんじゃないかなという気持ちがあります」と…。そう考えると、コピーライター歴1年のぼくは、まだまだひよっこです。
ですが、この1年間を通して少しずつ手応えのある取材ができるようになってきた実感もあります。
先日、とあるクライアントの社長と180分にもおよぶ長時間の取材をさせていただいたときのことです。取材が終わった瞬間、なんとなくこれまでにない爽快感がありました。そんな余韻に浸っていたところ、社長から「長い時間の取材でしたけど、すごく気持ちよく喋れました」と、言ってもらえたのです。
あとから取材の音源を聞き直してみたのですが、あいまいな質問の仕方や繰り返しの確認など、いわゆる無駄な会話がかなり少なかったのです。なかでも特徴的だったのが、「以前YouTubeでお話しておられた〜」とか「Xでも〇〇とおっしゃってましたが〜」という前提を伝えたうえで、さらに深掘りする質問ができていたことです。
これができたのは、やはり取材前の準備につきます。社長が発信されているXの投稿をひたすら追いかけましたし、YouTubeでアップされていた動画にもすべて目を通しました。そして、それを人に説明できる状態にまでインプットできていたことが大きいと思います。
この取り組み方は年齢や経験、技術とは一切、関係のない部分です。つまり、取材のスキルは自分の努力次第でいくらでも伸ばしていける、ということでもあります。
コピーライターの方はもちろん、お仕事で取材(ヒアリング)することがある方にとって、この記事が少しでもヒントになれば幸いです。ぼくと同じ過ちは犯さないように……いや、むしろ取材スキルは恥をかきながら、冷や汗を流しながら、ときには胃を痛めながら、学んでいくものなのかも知れません。
小澤 良祐
トゥモローゲート株式会社意匠制作部コピーライター。健康食品などを扱う通信販売の会社で営業企画として約10年つとめたのち、2023年に入社。35歳にして人生初転職を経験する。企業のWEBサイト制作を中心とした取材や執筆、企業のコンセプトコピーの考案などを担当している。
TEL 06-7167-3950