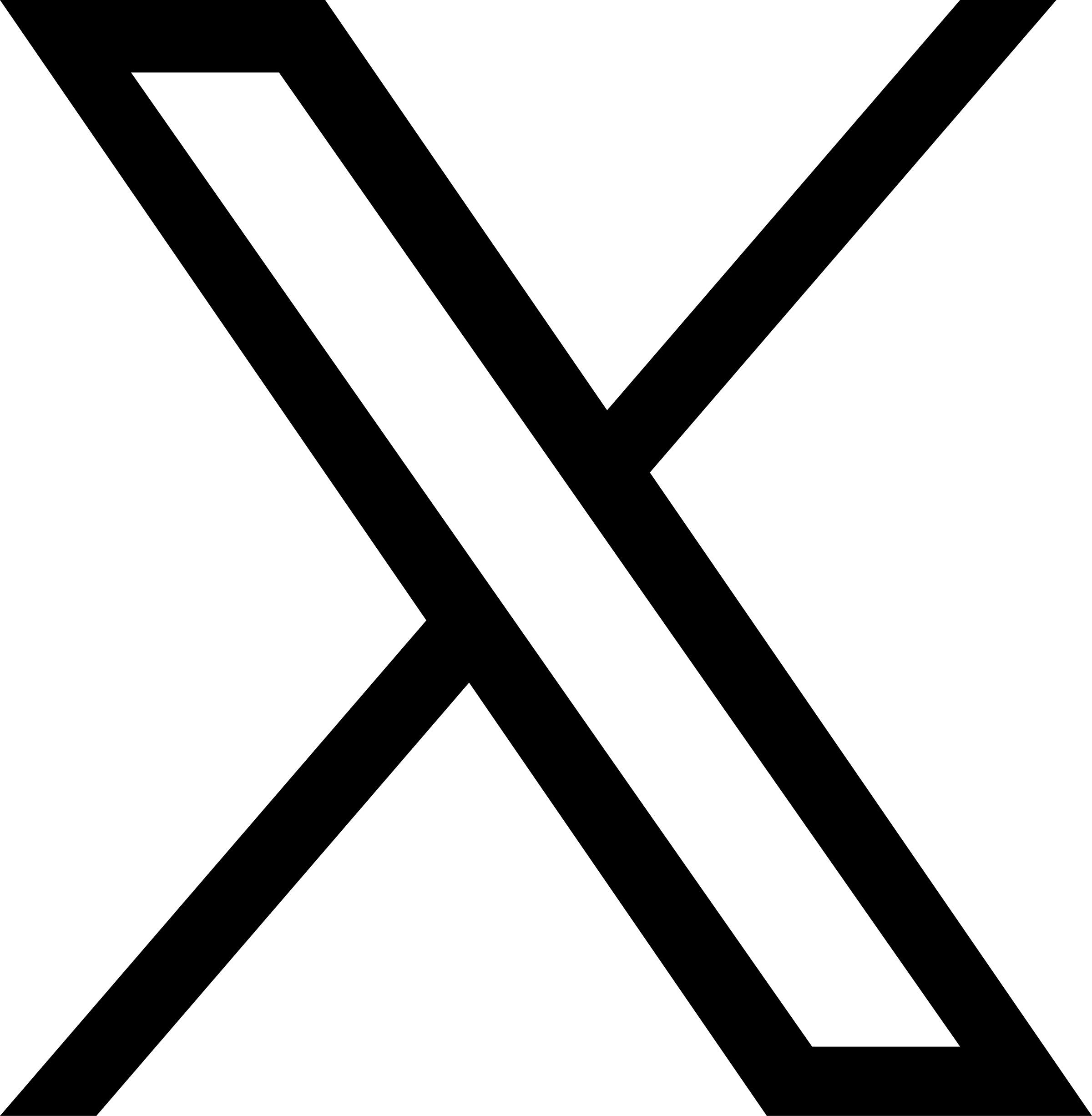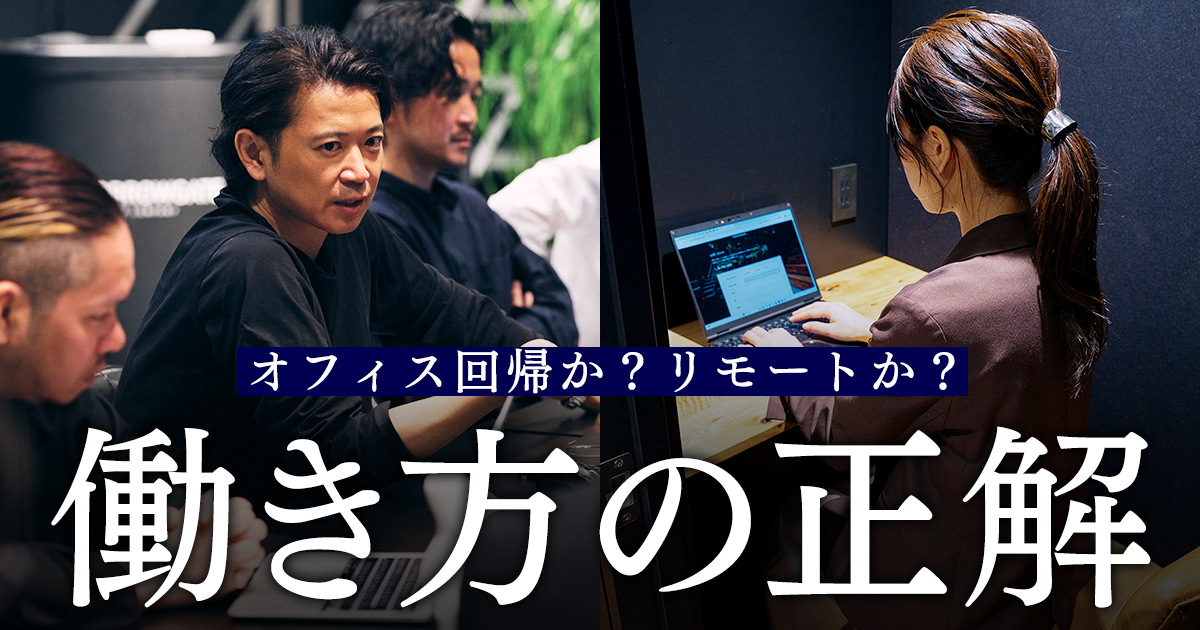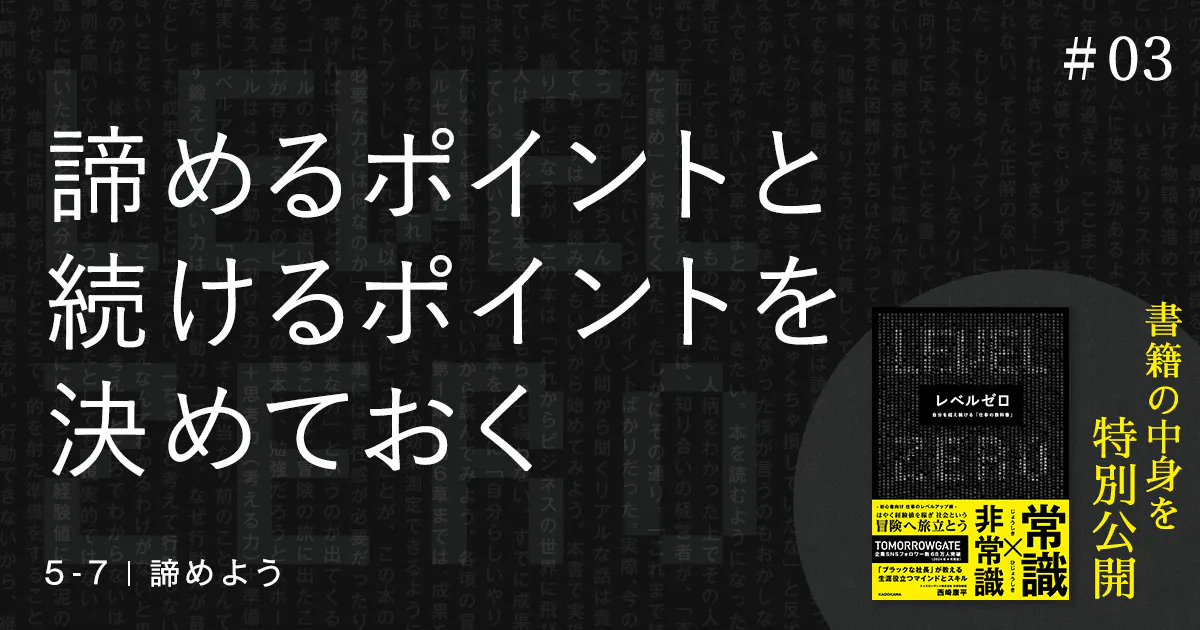「ブランディングに投資しているが、成果が出ているか分からない」
「評価指標が分からず、効果測定ができていない」
そんな悩みを抱える経営者やブランディング担当の方も多いのではないでしょうか。
実際、企業向けに実施された「ブランディングに関するアンケート(※)」では、約5割(53.3%)の企業が「ブランディング戦略の策定に至っていない」と回答。さらに、ブランディングを実施している企業の約2割(20.7%)が「評価指標を持っていない」と答えており、多くの企業が“手つかず”か、“測り方が分からないまま”ブランディングに取り組んでいるのが実態です。
※2024年度 ブランディングに関するアンケート(株式会社タナベコンサルティンググループ)より
ブランディングは、企業の中長期的な成長を支える重要な経営戦略。しかしながら、その効果をどのように測定し、改善につなげていくかは非常に難しい課題とされています。
そこで本記事では、
・ブランディングがもたらす効果
・ブランド力を計測するツール
・実際のツール活用事例
について具体例を用いながらお伝えします。ブランド力を“感覚”ではなく“データ”で捉えるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
そもそも「ブランディングの効果」とは?
ブランディングとは、企業が「誰に・どんな価値を約束するのか」を明確にし、その約束を体験として届け続けること。見た目のデザインを整えるだけがブランディングではなく、その根底にある“思想”や“哲学”こそがブランドの本質です。そのため、まず会社の理念(ミッション・ビジョン・バリュー)を言語化し、そこから一貫した体験やクリエイティブを設計することが必要です。
効果的なブランディングを行うことで、企業の「売上拡大・採用強化・社員定着」といった経営課題の解決にも直結します。
<ブランディングがもたらす効果>
・価格競争に巻き込まれず、金額以外の「価値」で選ばれるようになる
・経営理念への理解が深く、共感の強い「仲間」を集めることができる
・採用応募数や社員の定着率が高まり、「社内エンゲージメント」が向上する
ブランディングの効果測定が難しい理由
ブランディングには「明確な成果が見えにくい」という特性があり、多くの企業が「効果をどう測るか」を悩んでいます。なぜ測定が難しいのか、その代表的な理由がこちら。
・「定性的な成果」が多く数字にしづらい
ブランディングの難しさは、「成果がすぐ数字で出にくい」点にあります。広告のCTRやコンバージョンのように直接測れるわけではなく、認知や信頼、印象といった“定性的な成果”が多いからです。
・多岐にわたる要素が絡み合う「複雑性」
ブランドが企業にもたらす成果は、経営戦略、採用戦略、オフィス環境、組織文化など、さまざまな要素と相互に影響し合っています。そのため「どの施策が、どの成果につながったのか」を測るのは、非常に難しいと言われています。
・成果が出るまでに「時間」を要する
ブランディングは、目の前の反応を狙う広告とは異なり、時間をかけて“信頼”や“企業の姿勢”を育てていくもの。成果が見えるまでに時間を要するため、短期的な指標だけでは測りきれないという構造的なハードルがあります。
しかし、効果測定を行わなければ、現状の課題も改善の方向性も見えてきません。では、どのように測定していけばいいのか。ブランドの効果を数値化するための「有効的ツール」をご紹介します。
ブランディング効果測定に役立つツール
実務で効率的かつ正確に効果測定を行うには、ツールの活用が欠かせません。特に、近年ではサーベイツールなどを用いることで、ブランドの状態を多面的に可視化できるようになっています。
サーベイツールを選ぶ際のポイント
サーベイツールが多く選び方がわからないという声が多いのも事実。せっかくの調査が自己満足で終わらないよう、ブランドづくりに本当に役立つサーベイを選ぶためのポイントをお伝えします。
・「社員の理想」だけでなく「会社の理念」を基準に評価できるか
従来の組織サーベイは従業員満足度を測るものが多いですが、ブランド評価には企業が掲げる理念との整合性が欠かせません。
・「共感」だけでなく「行動」まで評価対象に含まれているか
ブランドは“想い”だけでなく、“実行”されてはじめて価値を持ちます。理念への共感が、日々の行動にどう落とし込まれているかを測る視点が必要です。
・調査結果が「改善」や「戦略」につながる構成になっているか
スコアの見える化だけでは不十分。分析結果をもとに「次にどう動くべきか」が示されるツールであることが重要です。
・理念・方針・行動など、ブランド構成要素を立体的に捉えられるか
ブランディングは一面的な評価では見えません。組織の内面(理念)から外部への発信(行動)まで、構造的に把握できる設計が求められます。
今回は、様々なツールの中でもこのポイントを押さえたブランド診断ツール「B-SCORE」をご紹介します。
ブランド力を可視化する「B-SCORE」(初回無料)
ブランディングの効果測定に有効なツールの一つが「B-SCORE」。ブランド構築に欠かせない3つのカテゴリ(理念・方針・行動)をもとに、全136項目の多角的な設問でブランド力を数値化します。経営理念だけでなく、職場環境や顧客との関係性など、ブランドを構成するさまざまな要素を可視化することで、現状の課題を明確にし、具体的な改善アクションへとつなげることが可能です。
<「B-SCORE」の特徴>
・ブランドづくりに必要な3つの要素「WHY(理念)・HOW(方針)・WHAT(行動)」を一括で測定できる
・理念への共感と行動を軸にした独自のシステムで、理念浸透と行動変容を伴う「本質的なブランド力の強化」に繋がる
・測定結果はスコア化され、視覚的に分かりやすいレポートで確認可能
・専門コンサルタントが数値から課題を分析し、改善策を提案するフォローアップ体制が整っている
▶︎B-SCOREの公式サイトはこちら
どのようにしてブランド力を測るのか
ブランドの効果測定ができるB-SCOREでは、指標として「理念・方針・行動」の3つの側面から評価するアプローチが有効的だと考えています。それぞれの指標について、詳しく説明します。
①会社の理想・現実(WHY)
ブランディングの起点は、「自分たちは何のために存在するのか」という“WHY”の問いに向き合うことから。この項目では、社員が感じている「会社の理想と現実」が、企業の掲げる「経営理念」とどれだけ一致しているかを測定します。「経営と現場の間にズレがないか」「社員が“自分ごと”として理念を捉えられているか」を可視化する指標です。
②方針の定義・共感(HOW)
次に、WHYで明らかにした理念が「どのようなブランド方針」として定義されているか。それが社員にどれだけ伝わり、共感されているかを測定するのがこのフェーズです。この項目では、「理念」「行動」「視覚」の3つの軸で、方針の明確さと共感度を評価。ブランドの“統一感”や“社内浸透”の度合いを知るための重要な指標となります。
③行動の実行・認知(WHAT)
定義されたブランド方針に基づいて、社員が実際にどれだけ行動できているか。そして、その行動や発信内容が、顧客や市場からどう認知・評価されているかを測定するのがこの指標。「言っていること」と「やっていること」が一致しているかの確認が可能です。
④総合スコアと偏差値評価
上記の3つのカテゴリ(WHY・HOW・WHAT)を総合的にスコア化し、ブランド力を定量的に可視化します。
実際にこのような構成で評価を行った企業では、理念の理解度が高い企業ほど行動実行スコアも連動して高くなる傾向が見られています。また「掲げている理念」と「実態」のギャップが小さい企業ほど、社外からのブランド認知スコアも高いという相関も見られています。
「WHY(理念)・HOW(方針)・WHAT(行動)」の3層からブランドを見つめ直すことで、「どこにズレがあるのか」「何を強化すべきか」を明確にすることが可能。経営層や従業員に対しても、“見える化”を実現できる手法として有効的です。
【事例】ブランドサーベイ「B-SCORE」を活用したビジョン浸透と行動の変革
最後に、このブランド力を可視化する「B-SCORE」を導入した企業事例をご紹介します。
ブランドサーベイの導入理由
沖縄県で福祉事業を多角的に展開する株式会社ライフデザイン様では、以前に採用ブランディング強化の一環としてトゥモローゲート(B-SCORE運営元)に相談してくださった経験があり、サービス導入への関心を高めていました。
また、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を策定してから一定期間が経過し、毎週の全社員向けオンラインミーティングなどを通じて理念浸透を図ってきたものの、実際にどれほど社内に定着しているのかを定量的に把握できていないという課題を抱えていました。
MVVを軸にしたサーベイはまだ珍しい手法であり、その新規性にも大きな期待を寄せていたため、ブランドサーベイ「B‑SCORE」を導入し、理念への共感度だけでなく、日々の行動にどれほど落とし込まれているかまで可視化することを目指しました。
サーベイを実施した結果
サーベイの結果、明らかになったのは「理念の共感度は高い」ものの、「“ミッション・ビジョン・バリューに沿った具体的な判断基準”や“ビジョン実現に向けたアクションプラン”との接続が弱い」という事実でした。
この結果をもとに、B-SCORE運営元(企業ブランディングを手掛けるトゥモローゲート)のコンサルタントが、さらなる組織改善に向けて施策をご提案。ライフデザイン社は、組織内での理念の浸透強化に向けたプロジェクトを開始しました。
施策として、元々策定されていたミッション・ビジョン・バリューを軸に定量目標までを言語化した「ビジョンマップ」を策定。ブランドの「理解」から現場レベルでの「体現」を強化していく、というステップアップに取り組まれています。
<実施したこと>
・中期ビジョンおよび達成要件、定量目標の策定
・全社の判断基準の再定義
・「ビジョンマップ」としてデザイン
※ビジョンマップとは:経営理念、大切にする価値観、具体的な行動施策などを細部まで言語化した「ビジョン達成までの道のりを示す一枚の地図」
担当者様のコメント

株式会社ライフデザイン 代表取締役社長 南 徹 様
これまで「理念は浸透しているのでは」という予想はありましたが、B‑SCOREでスコアとして定量的に可視化されたことで、全社に自信を持って共有できる成果に繋がりました。
MVV自体への共感度は非常に高く、浸透も進んでいる一方で、中期ビジョンや経営計画、採用計画といった具体的な“次の一歩”については、社員への説明をさらに強化すべき点が明らかになりました。
他社比較でも高いスコアを獲得したことで、これまでの施策の方向性に間違いがなかったことを確認でき、マネージャーやスタッフのモチベーションが大きく向上しました。
まとめ|ブランディングの効果測定は「可視化」と「継続」が鍵
ブランディングの成果は短期間では見えづらく、感覚的になりがちです。しかし、適切な指標とツールを活用すれば、その効果を客観的に測定し、次の改善につなげられます。まずは、ブランドの現状を“見える化”することから始めましょう。
今回ご紹介した「B-SCORE」は、そのための支援ツールとしてブランドの状態を多面的に把握する手助けとなります。
▶︎【初回無料】詳しくはB-SCORE公式サイトをご覧ください
よくある質問(FAQ)
Q1. ブランディングのKPIはどうやって決めればいいですか?
①ブランドの「ゴール」を明確にする
②ゴールに向けた「行動」を洗い出す
③行動を「数値」で追える指標に変換する
・認知度:SNSインプレッション数、指名検索数、PR露出件数など
・採用:会社の理念に共感した応募者の割合、説明会参加率、離職率など
・社内浸透:社内サーベイでの理念共感度スコア、行動指針の理解度など
・ブランド体験の向上:顧客満足度スコア、口コミ評価の質/量など
Q2. 経営層にブランディングの成果をどう説明すれば納得してもらえますか?
感覚的な印象ではなく、ブランドKPIやスコアの定量データを用いて可視化することがポイントです。「理念への共感度が上がった結果、離職率が低下した」など、数値と因果関係をセットで提示すると説得力が高まります。レポートにはグラフやコメント分析なども活用しましょう。
Q3. ブランディングの効果測定はどのくらいの頻度で実施すべきですか?
四半期に1回程度の定点観測がおすすめです。中長期でブランド施策の進捗や改善効果を把握しやすくなります。また、変化のタイミング(理念変更・組織改編・リブランディングなど)にあわせて臨時で実施するのも有効です。
Q4. 社内にノウハウがなくてもブランディングの効果測定はできますか?
はい。ブランド調査ツールや外部コンサルティングを活用することで、専門知識がなくても実施可能です。たとえば「B-SCORE」では、ブランディングの現状をスコア化し、コンサルタントによる改善施策の提案、伴走まで一貫して支援しています。
Q5. ブランド力の可視化にはどんなツールがありますか?
ブランド力の可視化には、理念に基づいた一貫した顧客体験を測れるツールが有効的です。今回ご紹介した「B-SCORE」は、会社の「理念・方針・行動」の3層構造でスコア化できるため、ブランディングが一貫した顧客体験につながっているのかを把握することに適しています。
田原 莉奈
TEL 06-7167-3950