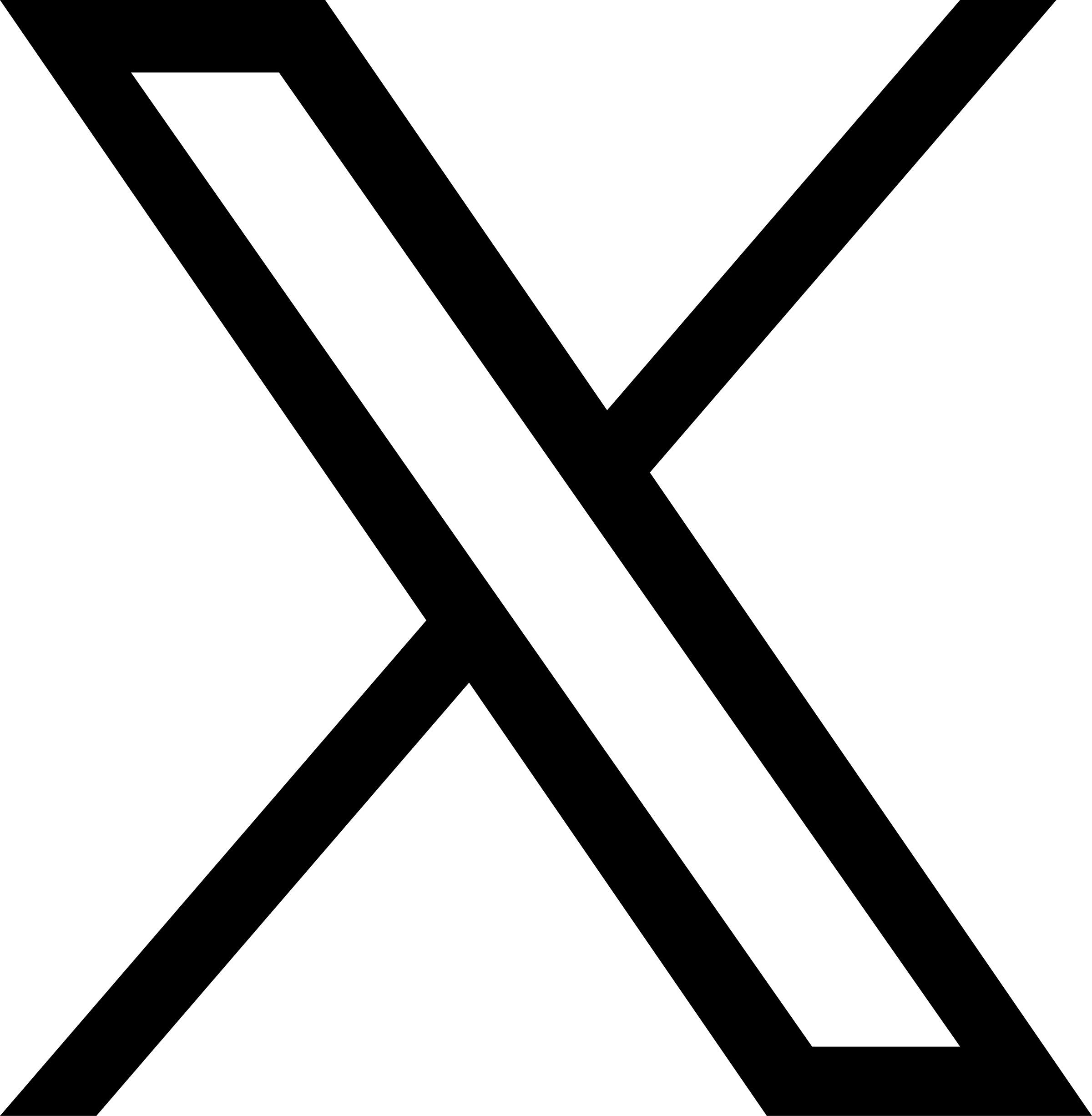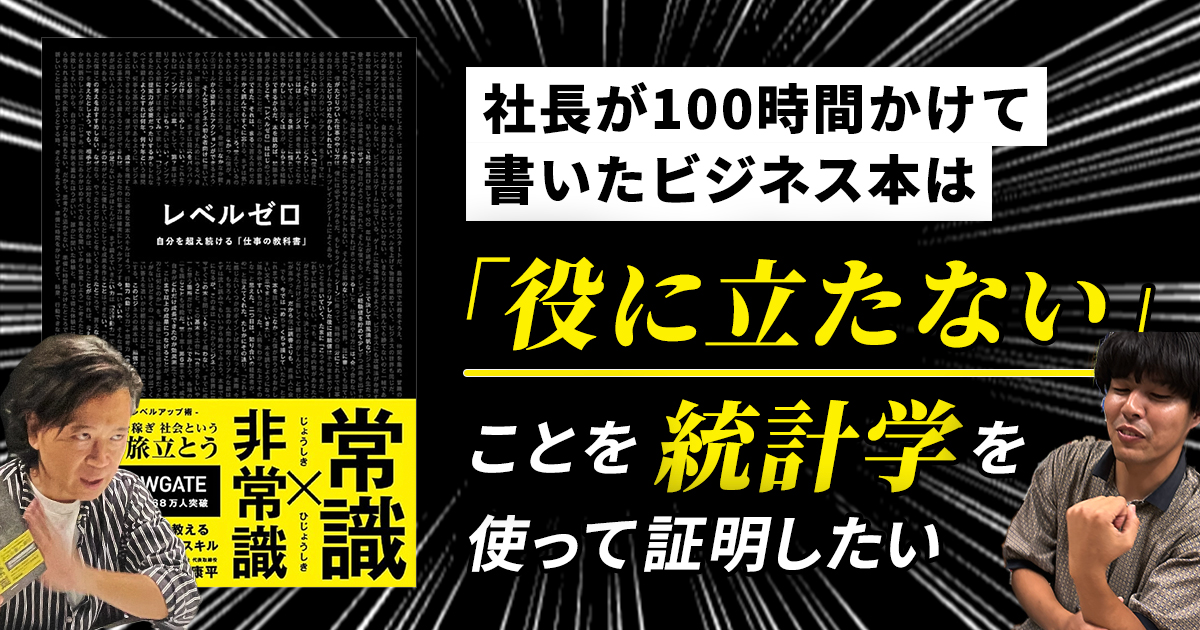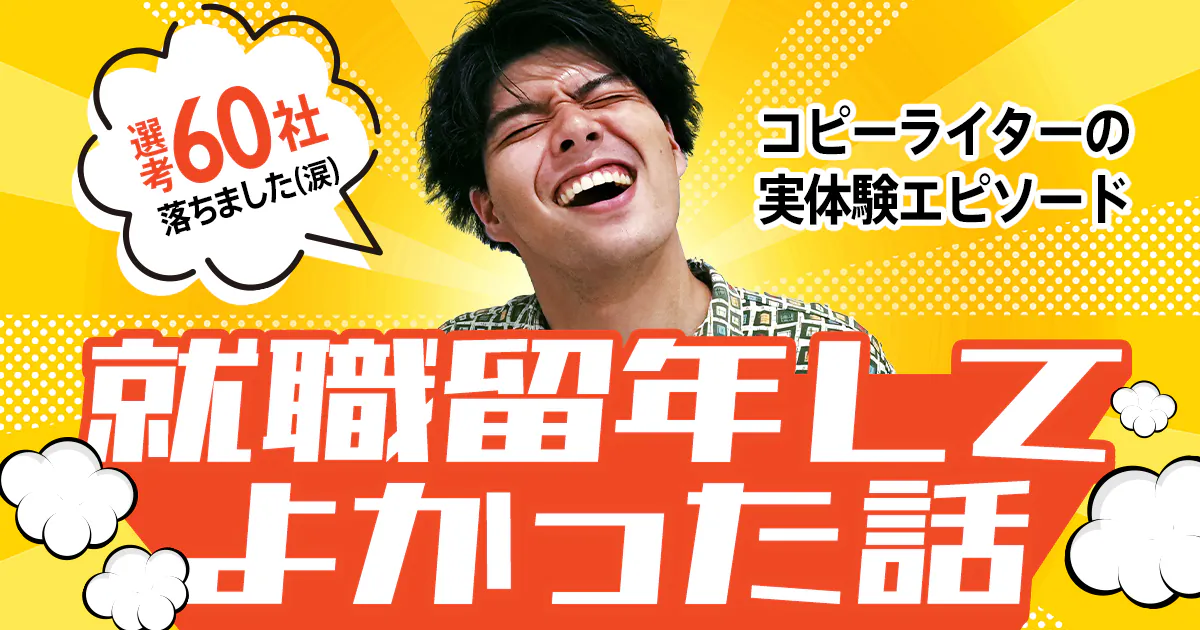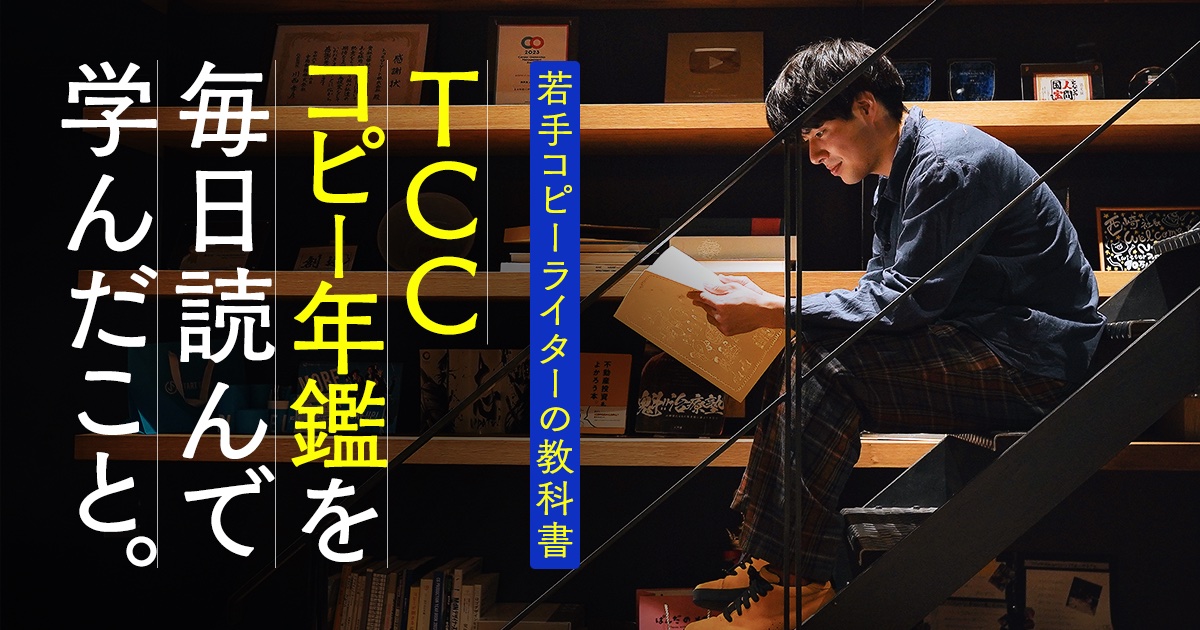
27歳、暇人の挑戦。
「新人コピーライターはまずTCCを写経しろ!!」
広告業界では、そう言われてよく勧められがちな「TCC写経」。
これって、本当なのだろうか。
曲がりなりにも「コピーライター」という肩書きを背負っている僕も、「TCC年鑑2年分を全文字写経する」挑戦をしていたことがあった。
(その頃の記事はこちら)
そして、小川サトキ、今年27歳。
休日を過ごすべき家族もいなければ、ろくな趣味もない。
時間だけを持て余した人間がふたたびTCC年鑑を手に取るのは、なんら不思議なことではなかった。
前回の「写経」の反省としては、「コピーを書き写すだけじゃもったいないな」ということであった。
写経を通じて足腰が強くなった気はするけど、その実感はあまりない。
だからこそ、次は目に見えない筋力ではなく、目にみえる武器として「コピー」をストックし広告制作に活かしたい。
そう考えて始めたのが「TCCマラソン(名付け親は自分である)」だった。
「TCCマラソン」とは、一体何なのか。
TCCマラソンとは。
「気に入ったコピーをひたすらメモしてストックする」。
これをTCC年鑑50年分続けるだけの作業である。
散々もったいぶった割には、広告業界ではメジャーなトレーニング方法だろう。
コピーと一緒に残しておく情報は、クリエイティブとクライアント名、そして「何が面白いと感じたのか」を一行でメモしたもの。
(TVCMやラジオなどだと、言葉以外にも映像や音声などの要素が「面白さ」に絡んでくるので、決して一行で説明できるものでもないのだが…)
とにかく、面白いと思ったものをストックし続ける。
一つの年鑑が500ページほどあるので、50年分となると25000ページの年鑑を読んだことになる。
今日この特訓方法を知った人にとっては「それが何の役に立つのか」と感じる人もいるかもしれない。
この時のキーワードは「構造の転用」だ。
「何が面白いのか」を構造化することで、いいコピーを「パクる」ことなく「参考」にする。
それが、マラソンの先にある成果である。
例えば、僕が撮って残しておいたコピー。
「日本では事故で亡くなるという。海外では『kill』という。」
(著作権の関係上、 実際のデザインを載せられないのがもどかしい…)
これは「AICHI SAFETY ACTION」という、交通事故の多い愛知県で交通安全を啓蒙するためのプロジェクトの広告である。
このコピーからは「外国語(異文化)に注目してみると、自分たちの考えの偏りに気づくのか」という気づきがある。
この考え方を転用することで、たとえば「中国から見た〇〇(クライアント)はどう見えるんだろう?」「この文化は外国からどう見えるんだろう?」と言った発想のきっかけになるかもしれない。
有名なTOTOウォシュレットのコピー
「おしりだって洗って欲しい。」
このコピーからは、「ネガティブな要素は、擬人化すると余計に伝わりやすくなる」ということがわかる。
このように、1000通りの技をストックしていけば、一つの商品で1000通りのコピーが書けるということである。(もちろん、これは過言である)
そしてこのTCCマラソン、実際に自分がコピーを書く時以外にも役に立った瞬間があるので一つずつオススメしていきたい。
お役立ちポイント①
正直、昔のコピーはもうわからん。(という発見)
広告は時代と共に移り変わる。
僕が好きなJR九州のコピー。
「愛とか、勇気とか、見えないものも乗せている。」
これは、どんな時代でも変わらない「鉄道」の価値を言い当てた不朽の名作である。
(もちろん、30年後の「電車」は全く違うものになっているかもしれないが…)
しかし、当時の流行りや口調、価値観に合わせたコピーだと「これって何がウケたんだろう?」と迷宮に陥ることも多い。
また、「これ、今なら炎上してるだろ…」というようなものも少なくない。
たとえば、Blendyの「姉の胸がふくらんで来た頃から、兄弟喧嘩は少なくなりました。」というコピー。
今の時代には、なかなか出せない広告だと思う。
でもこれは当たり前である。価値観は変わってゆくのだから。
(ちなみにこのコピーを書いたのは、「愛とか、勇気とか、見えないものも乗せている。」と同じ仲畑貴志さん。)
そして、この「わからん」ものを無理して「わかりにいく」過程に勉強が詰まっているのだと思う。
当時の時代背景はどうだったのか。商品を取り巻く環境はどうだったのか。
TCCを眺めながらそれを考えることが思考の筋トレにつながったように思う。
お役立ちポイント②
「抽象→具体」の思考トレーニングが身についた。
これは、コピーに限らず「人生」で役に立ったこと。
この特訓を通じて、「自分が何を面白いと感じるのか?」を言語化する習慣が身についたことはとても人生にプラスに働いたように思う。
たとえばM-1を見る時。
ただ反射的に笑うのではなく、笑った後に「今のツッコミって何が面白かったんだ…?」と自然と分析するようになった。
(小説を読むときもこんなことを続けているおかげで、本を読むのは倍くらい遅くなったのだが)
この分析を続けたおかげで、「自分は今何を考えているのか」をわかりやすい言葉に落とし込む能力が上がった気がする。
お役立ちポイント③
飲み屋でたいていのコピーの話ができる。
体感、コピーライター同士の飲み会は最終的にコピーの話に落ち着いていく。
それは、コピーライターの8〜9割はコピーライターという仕事が好きだからである。
だからこそ、飲み会で話題に上がった有名なコピーに対して「えっ、その広告は知らないです、、」というと、ほんのちょっとだけ空気に淀みが生じる(気がする)。
そして「こいつ、大したことないな」とナメられるんじゃないかと感じてしまう。
(感じてしまうだけで、実際は被害妄想なのだが、、、)
「TCCマラソン」をやる大きなメリット。それは、コピーライター同士で過去の広告の話になった時、だいたい「ああ、あれね」とついていけることなのである。
そしてそれは、精神衛生上大変よいことである。
ああ、なんて不毛なのだ。気にしてるの俺だけか。
もちろん、社内の打ち合わせで「今回作りたいのはあの広告のイメージだよね」というのも飛び交うので、過去の事例を知っておくのはコピーライターにとっては必須だ。
(というか、こっちのほうが100倍大事か)
正直、「本当に役に立ったのか?」はわからない。
ここまで、「TCCマラソン」のいいところについて語ってきた。
それなりに経験を積まれているコピーライターの方なら、「こいつは何をずっと当たり前のこと言ってるんだ」という内容だっただろう。
ただ、「そのTCCマラソンとやらは役に立ったの?」と聞かれると、結局「まあ…それなりには…?」という歯切れの悪い返答をせざるを得ないのだ。
というのも、このコピーのストックたち。
発想のトリガーになることはあるが、「このコピーのおかげでこれが書けたぞ!!」と明確な一手になった覚えはないからだ。(「がむしゃらに考えているから、どれが明確な一手かわからない」というのもありそうだが)
と、いうより。事例が脳内で自然と思い出せるようになったせいで、「これはTCCマラソンのおかげだ!」という恩恵に気づけない、というのも大いにあると思う。
結局、コピーは足腰ゲーなのかもしれない。
約1年間、土日を消し飛ばした先に。
ついでにこの「TCCマラソン」、かなり時間がかかる。
「土日の昼間をTCCインプットにあてる」と決めたら、読み切るまでに大体1年かかった。
というか今改めて数えたらこんなにかかっていたことに気づいた。血の気引いたよ。
しかしそのおかげで、コピーライターの基礎中の基礎の力は身についた。
(というより、これをやらないことにはコピーライターとしては何も始まらないと感じている)
トゥモローゲートのコピーライターの仕事は「企業の軸となるコンセプトやスローガンを書くこと」。
一発の爆発力を狙う広告コピーとは「ことばの狙い」が違うかもしれない。
しかし「コピーライター」を名乗る以上は、広告を作る機会を増やさなくてはならない。
そう考えて「TCCマラソン」に踏み切ったからこそ、力を身につけることができた。
だからこそ、今コピーライターを目指している人も、コピーライターになり立ての人も。
一度「マラソン」をやってみるのもいいかもしれない。
70年分とは言いませんが…20年分くらいなら、2か月もあればできるはず。ぜひぜひ、取り組んでみてください。
最後に!
トゥモローゲート株式会社では、現在コピーライターを募集しています!
経験者の方はもちろん、未経験であってもそれを吹き飛ばすような熱意がある方、大歓迎です!
(実際、僕も未経験から入社しています)
TCC年間を一緒に愛でる仲間を求めています。ぜひこちらからご応募ください!
小川 聖樹
トゥモローゲート株式会社意匠制作部ライター。一度は新卒でWEB広告会社に営業職として入社するも、コピーライターの夢を諦めきれずトゥモローゲートに1年で転職。パンフレットやWEBサイトなどのコンテンツ企画やテキストライティング、企業のコンセプトコピー開発などを担当する。
TEL 06-7167-3950