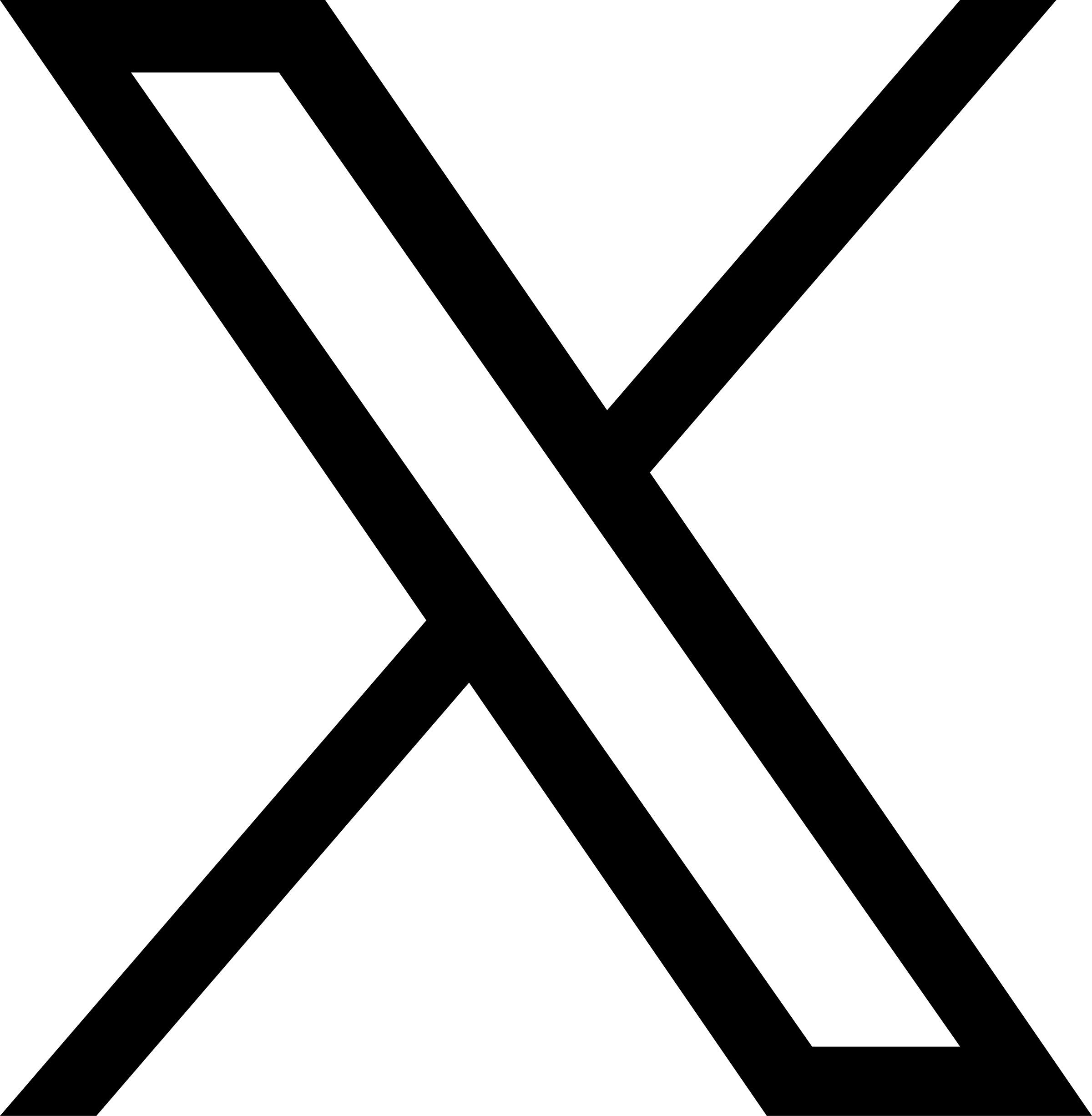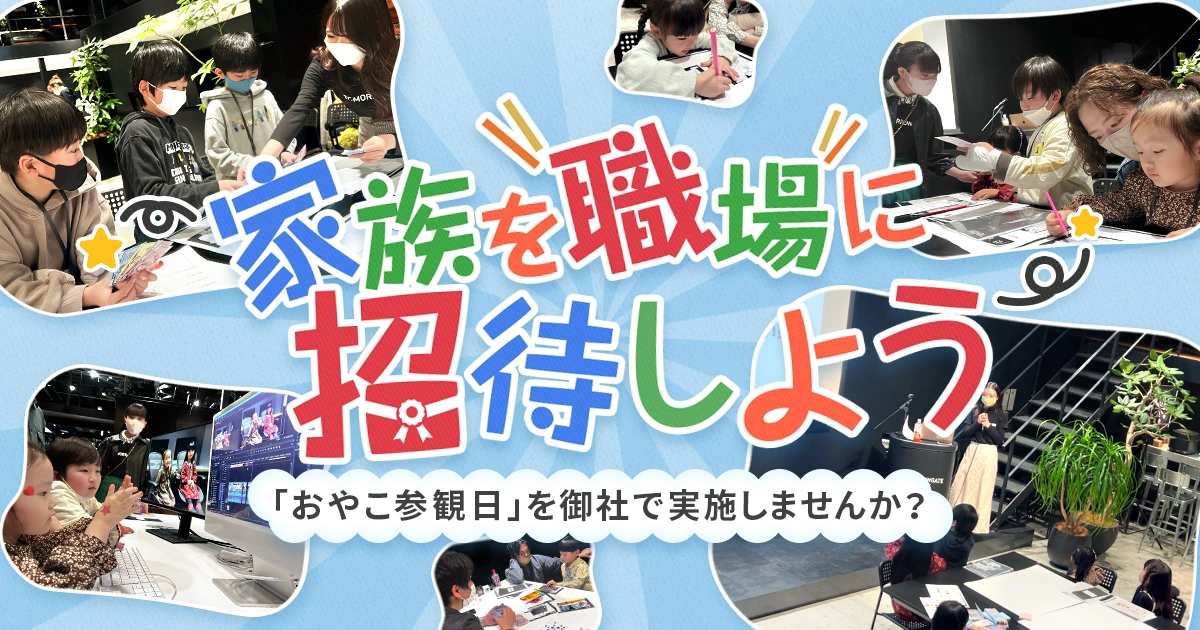採用に関して、このようなお悩みをよくいただきます。
「そもそも応募が集まらない」
「内定を出しても辞退されてしまう」
「今以上に質の高い方を採用したい」
ここで必要になるのが「ターゲットから“貴社だから”と選ばれる、比較されない企業づくり」です。そのための手段として、経営理念の策定から採用ツールまでを一貫して行うプロジェクトとしてご提案することが多くあります。
するとこんな質問をいただくんですよね。
「採用ツールと経営理念の策定、どちらを優先すべきか?」
「同時並行で進めると、かえってギャップを生んでしまうのではないか?」
しかし、結論から言うと――
経営理念がなくとも、採用ツールは制作できます。
たしかに、理念が「ある」か「ない」かによって、採用において発揮できる“強み”の質が変わります。ただし、伝え方さえ注意すれば、理念策定と採用ツールを同時並行で進められます。
この2点が、今回お伝えしたい最大のポイントです。
経営理念が採用に好影響を与える理由
経営理念は、単に企業の存在意義や価値観を社内に示すだけのものではありません。
採用においては、「どんな人材を求めているのか」や「入社後にどんな働き方をしてほしいのか」を明確に伝える軸になります。この軸があることで、採用活動全体に一貫性が生まれ、求職者は会社の方向性を理解しやすくなります。
▶︎経営理念の策定方法はこちら
①一貫性のあるメッセージが構築できる
理念が明確に定められていると、採用の軸もはっきりします。たとえば、採用媒体での文章をはじめ、各ツールのデザイン、写真、コンテンツなどすべてが、「どんな価値観を大切にしている会社か?」という問いに対して一貫した答えを持てるようになる。それによって、ターゲットから信頼される、ささるメッセージが発信できるのです。
②他社と比較されない“自社らしさ”が生まれる
なによりも大きなメリットは、他社と比べようがない“自社らしさ”ができること。
給与や福利厚生といった条件面で差別化をした場合、もちろん募集は増えると考えられます。一方で条件のみが志望理由になると、「A社の方がお給料がいいから辞める」「福利厚生が充実してるB社に内定承諾をだそう」と完全なる投資競走になってしまいます。
だからこそ、「考え方」や「組織の文化」を軸に訴求することはその会社“だから”働きたいという気持ちを掻き立てられる武器になります。

採用ブランディングにおいて本当に必要なものとは?
前述の通り、採用ツール制作において理念があった方がより優位ではあります。ただ、ここで注意したいのは理念策定も1つの手段に過ぎないこと。
要するに、「ブレない軸」さえあれば問題ないのです。そのため、弊社では理念策定せずとも採用の「ブランドコンセプト」として軸を定めた上で制作をさせていただいています。
ブランドコンセプトは「企業の“どんな魅力”を、“誰”に対して“、どのように”打ち出すのか」を具体化したもの。ここが曖昧なままデザインやコピーだけ整えても、応募は一時的に増えても定着しない・カルチャーフィットしないという課題に直結します。
▶︎実際の採用ツール制作実績はこちら
【事例】軸を定めず採用を進めた結果
理念が未策定のまま採用ツール制作を進めると、どのようなことが起きるのか。
実際の事例をお伝えします。
ある企業では、私たちが関わる前から採用活動に力を入れていました。しかし、経営理念や価値観を細部まで言語化せず打ち出しに特化されていたため、応募は一部集まるものの、選考の歩留まりや入社後の定着率が伸び悩む状況が続いていました。
そこで弊社にご相談をいただき、まずはミッション・ビジョン・バリューの策定をご提案。その理念をもとに採用コンセプトの構築を行いました。そして、それらを反映させた採用サイトの全面リニューアルを実施。
結果として、応募者の志望動機が条件面ではなく理念や価値観への共感にシフトし、入社後の定着率も着実に改善。採用活動が「数を集めるための取り組み」から、「会社に共感してくれる仲間を迎えるための取り組み」へと変化しました。
つまり採用ブランディングは「見た目」からではなく、軸となる「理念やコンセプト設計」から着手することが成功の近道です。
▶︎コンセプト設計の詳細はこちら

理念策定と採用ツール制作を同時進行する場合
ここまで理念の有無による影響をお伝えしてきましたが、最後に「同時並行で進めると、反ってギャップを生んでしまうのではないか?」という問いについてお伝えします。
浸透している“テイ”で打ち出すのであればおっしゃる通り。ギャップを生みます。
よく耳にする失敗談として、“うちはこんな理念を皆で大事にしている会社です”と言い切ってしまうこと。理念をつくったらからには前面に押すべきだと考えるのは当然ですし、大事にしていると断言すべきです。
ただ、“すでに浸透している”と言ってしまったとしたら、それはミスブランディング。「あんなに皆で体現してると言ってたのにやっていないじゃん。」と離職に繋がりますよね。
だからこそ、同時並行で進めるのであれば
「この理念を大事にしている。ただ、まだまだ全員でできている会社ではない。だからこそ、理念通りの組織へと一緒につくりあげる一員になってほしい」
このように伝えたいものです。
理念を前面に出したい理由は「共感者(=ファン)」を採用するため。つまり、理念に対する現状の浸透具合を大きく魅せる必要はないのです。むしろありありと実態を伝えることで「自分が浸透させる人なる」と自分事として考えてくれる社員を生み出せると考えています。

まとめ
採用ブランディングにおいては、経営理念やコンセプトといった「ブレない軸」が必要であること。そして、経営理念の策定と採用ツール制作を同時に進める場合、浸透度合いを大きく魅せる必要はないということ。この2点を解説させていただきました。
とはいえ、「大きく魅せる必要はない」はどのブランディングにおいても共通する点ですね。
採用ブランディング事例のブログも発信していますので、ぜひ具体的な事例もこちらからご覧ください。
採用に困っているけれどどこからスタートしていいかわからない、自社の場合はどうなのか、など少しでも気になってくださった方はぜひお気軽にご連絡をいただけますと幸いです。ご状況にそって最適なフローをご提案させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
▶︎採用に関するご相談はこちら
大西 麗美
トゥモローゲート株式会社戦略企画部ブランディングプロデューサー。2021年に新卒入社。16企業の新入社員全44名がファン増加数を競うSNS企画を主催し、計17000名のフォロワーを増加させた。現在は、新入社員から役員まで年間のべ1500人の理念浸透研修の担当に加え、営業からコンサルティング、自社SDGs事業など幅広い領域で活躍。
TEL 06-7167-3950